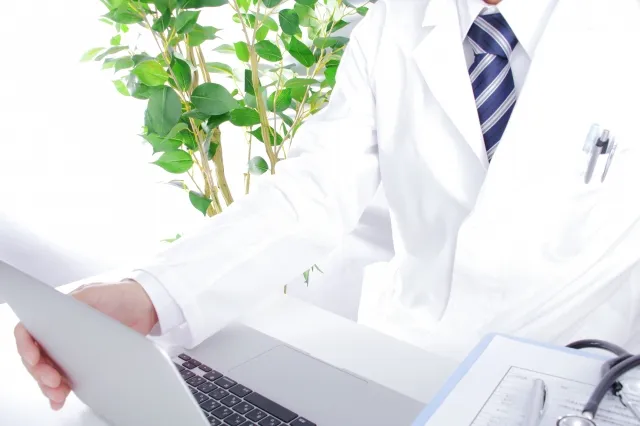開業資金は診療科目ごとに異なるため、ご自身が開きたいクリニックにかかる費用を把握することが大切です。
本記事では、診療科目ごとの開業資金の目安を、資金の調達方法とともに紹介します。
クリニックの開業に向けて、現実的な資金計画を立てたい方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:開業医とは?やりがいやメリット・デメリットを詳しく解説!
クリニック開業をご検討の医師の方へ
マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。
また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
まずは、サービス概要と案件情報をご覧ください。
目次 閉じる
クリニックの開業に必要な資金の目安

クリニックを開業するために必要な資金は、診療科目や開業する地域、また設置する医療機器などによって変わります。
一般的な目安は5,000万〜1億円程度であると考えられますが、CTやMRI装置を導入する場合は、2億円を超える場合もあります。
このような開業資金は、融資を受けることで確保できますが、開業後しばらくは収入が見込めない可能性もあるため、運転資金としてある程度の自己資金が必要です。
自己資金は、開業資金の1〜2割を目安に用意するとよいでしょう。
クリニックの開業にかかる費用の内訳

ここまで、クリニックの開業には多額の費用がかかることをお伝えしましたが、具体的な費用の内訳は気になるところではないでしょうか。
クリニックの開業資金の内訳は、以下の通りです。
クリニックの開業資金の内訳
- 敷金・礼金
- 先払い家賃
- 仲介手数料
- 内装工事費
- 診療設備費
- 医療機器購入費・リース費
- OA機器購入費
- 消耗品費
- 集患・広報費
- 採用・研修費
- 医師会諸経費
- 人件費
上記のほかに、経営が安定するまでの運転資金も用意しておくとよいでしょう。
クリニックを開業した直後は、患者数を十分に獲得できない可能性もあります。
手元に運転資金があれば、開業初期の資金繰りの悪化を防げるかもしれません。
診療科目によって異なるクリニックの開業資金

前述の通り、クリニック開業に必要な資金は、診療科目によって異なります。
以下に、診療科目ごとの開業資金の目安をまとめたので、参考にしてください。
診療科目ごとの開業資金の目安
| 診療科目 | 開業資金の目安 |
| 内科 | 5,000万〜8,000万円程度 |
| 小児科 | 4,000万~6,000万円程度 |
| 産科・婦人科 | 5,000万~6,000万円程度 |
| 泌尿器科 | 3,000万~1億円程度 |
| 皮膚科・美容皮膚科 | 2,000万~1億円程度 |
| 耳鼻咽喉科 | 4,000万〜8,000万円程度 |
| 整形外科 | 5,000万~1億円程度 |
| 精神科・心療内科 | 1,500万〜3,000万円程度 |
| 脳神経外科・内科 | 6,000万〜2億5,000万円程度 |
上記の表を見ると、必要な開業資金がもっとも少ないのは精神科・心療内科であり、反対にもっとも高いのは脳神経外科・内科であることがわかります。
では、診療科目ごとの開業資金の詳細を見ていきましょう。
内科
内科クリニックを開業する際に必要な資金は、5,000万〜8,000万円程度です。
開業資金の目安に幅がある理由は、内科の専門分野によって開業資金が異なるためです。
内科の専門分野の例
- 一般内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 内分泌・糖尿病内科
一般内科は、そのほかの内科と比べて治療に使用する診療機器の種類が少ないため、開業資金を抑えられる傾向にあります。
しかし専門分野を診る内科の場合、専用の医療機器を用いることから、その分の導入費用が発生します。
たとえば、消化器内科の場合は上部・下部の内視鏡が必要であり、内分泌内科では超音波診断装置を用意しなければなりません。
小児科
小児科クリニックの開業資金の目安は、4,000万〜6,000万円程度です。
小児科には、乳幼児が遊びながら待つことができるキッズスペースの設置が求められます。
また、ご家族全員で来院する場合も多いので、駐車場も用意できると理想的です。
これらを考慮すると、比較的広い院内のスペースと駐車場を設けるための敷地が必要となり、その分費用がかさむ傾向にあります。
産科・婦人科
開業したいクリニックの診療科目が、産科・婦人科であれば、開業資金の目安は5,000万~6,000万円程度です。
産科・婦人科には、超音波診断装置の設置が求められます。
さらに不妊治療や出産にも対応できるクリニックを目指す場合、より多くの医療設備の導入が欠かせないため、多額の資金を用意しなければなりません。
また、付き添いの男性の来院を認める場合は、ほかの女性患者さんと待合室を分けるなどの配慮が求められるため、広いスペースが必要になるでしょう。
泌尿器科
泌尿器科クリニックを開業する場合は、3,000万~1億円程度の資金が必要になります。
開業資金の目安に開きがあるのは、導入する機器によって費用が変動するためです。
尿分析装置・膀胱鏡・超音波画像診断装置・尿流量測定装置・結石破砕装置といった専門的な医療機器をすべて揃える場合は、多額の費用を用意しなければなりません。
また、泌尿器科は集患が安定するまでに時間がかかることもあるため、最低でも半年分の運転資金を用意することが理想的といえます。
皮膚科・美容皮膚科
皮膚科クリニックを開業する場合は2,000万~6,000万円程度、また美容皮膚科を開業するのであれば5,000万~1億円程度の資金が必要です。
保険診療のみを実施する皮膚科では、高額な医療機器や広いスペースがなくても開業できる可能性があります。
一方で、自由診療を実施する美容皮膚科では、治療でレーザー機器を用いるため、用意するべき開業資金も多くなります。
関連記事:皮膚科の開業医の平均年収は?成功するためのポイントも解説
耳鼻咽喉科
開業するクリニックが耳鼻咽喉科の場合に必要な資金は、4,000万〜8,000万円程度です。
耳鼻咽喉科の医療機器にかかる費用は、手術対応やCT装置導入の有無によって異なるため、開業資金の目安に差があります。
耳鼻咽喉科では、内視鏡・超音波検査装置・ネブライザーが必要になるほか、患者さんが患部を確認できるモニターを設置する場合もあるでしょう。
また、聴力検査用の防音室も設置しなければならないため、広いスペースが必須になり、開業資金も高額になることが多いというわけです。
整形外科
開業を考えているクリニックの診療科目が整形外科の場合は、5,000万~1億円程度の資金が必要です。
導入するリハビリテーション設備を最低限に抑えるのであれば、初期費用を節約できます。
反対に、リハビリテーションに幅広く対応できるクリニックを開業したい場合は、物理療法用の医療機器の導入のほか、理学療法士や作業療法士の採用も必須になります。
そのため、充実したリハビリテーションを提供する場合は、多額の費用が必要になるというわけです。
なお、対応する検査の規模によっては、骨密度測定装置やMRI装置といった検査機器の設置も求められるため、医療設備費がより高額になる可能性があります。
精神科・心療内科
精神科・心療内科クリニックを開業するために必要な資金は、1,500万〜3,000万円程度で、ほかの診療科目と比べると少額といえます。
これは、精神科・心療内科にはレントゲンやCT装置などの大型医療設備が不要なためです。
とはいえ、患者さんのプライバシーを保護するための設備費用は、しっかりと確保する必要があります。
精神科・心療内科の患者さんのなかには「自分の診察内容を、他人に聞かれたくない……」と考えている方も多いため、診療時の声が漏れないように配慮することが大切です。
たとえば、診療室と待合室のあいだに壁を設ける、または吸音性の高い素材を壁に用いるといった工夫が求められます。
精神科・心療内科クリニックを開業する際は、内装にかかる費用を惜しまないようにすることで、集患できる可能性が高くなるといえます。
脳神経外科・内科
脳神経外科・内科クリニックを開業したい場合は、6,000万〜2億5,000万円程度の資金を用意するのが理想的です。
CTやMRI装置を導入するかどうかによって医療設備費が大きく異なり、それらを導入する場合は多額の費用を用意する必要があります。
開業地域の病院と連携して、CTやMRI装置を導入せずに開業することで、費用を抑えるというのも一つの方法です。
クリニック開業をご検討の医師の方へ
マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。
また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
まずは、サービス概要と案件情報をご覧ください。
クリニック開業時の資金を調達する方法

ここまで、診療科目別の開業資金について解説しました。
ご自身のクリニックの開業に必要な費用がイメージできたところで、資金の具体的な調達方法を押さえておきましょう。
以下で、クリニック開業時に有効な資金調達の方法を6つ紹介します。
日本政策金融公庫
クリニックを開業する際には、日本政策金融公庫から融資を受けるという方法があります。
日本政策金融公庫とは、民間の金融機関が行う金融を補完し、新しい事業を立ち上げる事業者をサポートする政策金融機関です。
同機関は、“新規開業・スタートアップ支援資金”とよばれる融資制度を提供しており、対象となるのは新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方です。
この融資制度を利用すれば、7,200万円までの融資を受けることができ、そのうち4,800万円までを運転資金として活用できます。
返済期間は、設備資金が20年以内、また運転資金が10年以内に設定されており、どちらにも5年以内の措置期間が設けられています。
金利は担保や保証人の有無などにより変わりますが、民間の金融機関と比べると低いのが特徴です。
特に、女性の方・35歳未満または55歳以上の方は好条件で利用できる可能性があるので、この制度の利用を検討してもよいでしょう。
独立行政法人福祉医療機構
クリニックの開業を検討している方は、独立行政法人福祉医療機構の“医療貸付事業”の融資を利用するという方法もあります。
独立行政法人福祉医療機構は、国と連携して福祉医療の基盤を整備するための事業を展開する機構です。
医療貸付制度の融資では、建築の有無や有床・無床などによって融資条件が異なります。
たとえば、有床クリニックを新築する場合の限度額は5億円であるのに対して、無床または歯科クリニックを新たに建築する際の限度額は3億円です。
この制度の融資限度額は比較的高くて便利であるため、利用することも一案です。
民間の金融機関
クリニックの開業資金を調達するために、銀行や信用金庫といった民間の金融機関から融資を受けるという選択肢もあります。
民間の金融機関の融資条件は多種多様です。
なかには医療関係者の開業に特化したプランを提供する金融機関もあるため、複数社を比較したうえで最適なものを選ぶとよいでしょう。
医師会
医師会から融資を受けて、クリニックを開業するのも有効です。
各都道府県の医師会は、医師信用組合や地方自治体などと連携して、クリニックを開業したい方に向けた“開業支援ローン”を用意しています。
これにより、設備資金や運転資金といった多額の資金の借入が可能ですが、医師会への入会が条件となります。
すでに医師会に入会されている方や、今後入会する予定がある方は、開業支援ローンの利用を検討するとよいでしょう。
地方自治体
地方自治体の“制度融資”でも、クリニックの開業資金の借入が可能です。
制度融資は、金融機関と比べて低金利なので、長期にわたって安定して資金を調達できます。
自治体によっては、支払う利子の一部や信用保証料の一部を負担してくれるところもありますが、多額の資金調達には向かない可能性があります。
制度融資の利用を検討している場合は、各自治体によって手続きの流れや条件が異なるため、地域と連携している金融機関に問い合わせてみてください。
国・地方自治体の補助金・助成金
上述した制度融資のほか、国や各自治体が用意している補助金・助成金の制度があります。
以下にそれらの例をまとめたので、ご参照ください。
国・地方自治体の補助金・助成金制度の例
| 補助金・助成金制度の名称 | 概要 |
| 創業補助金 | 創業時に必要な経費の一部を補助する制度 |
| 事業承継・引継ぎ補助金 | 医院継承で開業した際に受けられる補助金制度 |
| IT導入補助金 | ITツール導入時に費用の一部を補助する制度 |
| 医療施設等施設・設備費補助金 | へき地医療の確保を主な目的とした補助金 |
| ものづくり補助金 | 医療機器や器具などの設備費用に関する補助金制度 |
上記のような補助金・助成金制度を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
また、クリニックの開業資金を補助金・助成金だけでまかなうのは難しいため、ほかの融資と組み合わせて利用するとよいでしょう。
レンタル・リース会社
医療機器レンタル・リースの会社のなかには、融資やローンのサービスを提供しているところもあるため、それらを利用するのも一案です。
これらのサービスは主に、クリニックを新規開業する方や、海外製または中古品といったリース契約の対象外となる医療設備を購入する方向けに展開されています。
また、融資やローンを利用しない場合でも、医療機器をリースすることで、初期費用を抑えられるほか、リース料を経費として処理することもできます。
提供しているサービスは各レンタル・リース会社によって異なるため、比較検討したうえでご自身に合った方法を選びましょう。
クリニックを開業する際のポイント

クリニックを開業する際は、資金以外にもいくつかの留意点があります。
ここからは、クリニックの開業に際して、覚えておきたいポイントを紹介します。
ポイント①事業計画書の作成
クリニックを開業するときに欠かせないのが、事業計画書です。
経営の基本計画・資金計画・収支計画をまとめた事業計画書を作成することで、経営の見通しが立ちやすくなります。
事業計画書は、開業資金の借入時にも提出することになり、その内容によって返済能力の有無が判断されます。
そのため、ご自身の事業計画の信憑性をアピールできるように、事業計画書を作成する必要があるのです。
ポイント②各種申請
クリニックを開業するためには、さまざまな書類を行政機関に提出しなければなりません。
以下に、クリニック開業の際に必要な書類をまとめました。
行政機関ごとの提出書類
| 提出先の行政機関 | 必要となる提出書類 |
| 保健所 |
|
| 厚生局 |
|
| 地区医師会 |
|
| 消防署 |
|
| 税務署 |
|
| 都道府県税事務所 |
|
| 社会保険事務所 |
|
| 公共職業安定所 |
|
| 福祉事務所 |
|
| 労働基準監督署 |
|
上記の、保健所に届け出る“診療所開設届”は、開設後10日以内の提出が医療法で義務付けられています。
また、診療所開設届の受理後に、“保険医療機関指定申請”を厚生局に提出しなければ、保険診療ができないのでご注意ください。
ポイント③マーケティング戦略の策定
クリニックを開業するのであれば、マーケティング戦略について考える必要があります。
代表的な集患方法として、SEO対策・MEO対策・SNS運用が挙げられます。
SEO対策とは、検索エンジンにおいて自院のホームページが上位表示されるように最適化することです。
対してMEO対策とは、地図検索サービスにおいて上位表示を目指すための対策です。
また、自院の認知度を高めるためには、SNSを効果的に運用することが望ましいでしょう。
クリニックの集患のためにも、このようなマーケティング戦略は重要といえます。
クリニックの開業資金は、診療科目によって異なる

今回は、クリニックの開業資金の目安やその調達方法を解説しました。
クリニックの開業に必要な資金は、診療科目や導入する医療設備によって異なります。
また、開業資金を調達する際は、民間の金融機関から融資を受けるほか、国や地方自治体の制度を利用する方法もあるので、比較検討したうえでご自身に合った方法を選びましょう。
開業のための資金調達にお悩みの方は、クリニック開業サポートの利用がおすすめです。
マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートは、事業計画書の作成から資金調達、開業後のフォローまで、一連の流れをすべて支援します。
まだ開業時期や資金計画が明確でない場合でも、ぜひお気軽にご相談ください。
クリニック開業支援ならマツキヨココカラクリニック開業サポート