特に耳鼻咽喉科は、子どもから高齢者まで幅広い年代の患者さんが訪れる診療科のため、開業後は地域医療に深く関わることができます。
本記事では、耳鼻咽喉科の開業を成功に導くポイントや、開業に必要な資金について解説します。
クリニック開業をご検討の医師の方へ
マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。
また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
まずは、サービス概要と案件情報をご覧ください。
目次 閉じる
耳鼻咽喉科の開業資金

耳鼻咽喉科を開業するには、一般的に4,000万~8,000万円程度の資金が必要です。
これには、契約する物件の費用や導入する医療機器の費用などの初期費用にくわえ、開業後の人件費や水道光熱費などの運営費用も含まれます。
それぞれの内訳を、以下で詳しく見ていきましょう。
初期費用
耳鼻咽喉科を開業する際の初期費用の目安は、4,000万~6,000万円程度です。
物件の内装や導入する設備などによって必要な資金は大きく異なるため、ここでは一般的な初期費用の例を紹介します。
耳鼻咽喉科を開業する際の初期費用の例
| 項目 | 費用 |
| 物件関連(敷金・礼金・保証金など) | 600万~700万円 |
| 内装工事(設計・施工) | 1,000万~3,000万円 |
| 設備(医療機器・家具・家電など) | 2,000万~3,000万円 |
| システム(電子カルテ・予約システムなど) | 300万~800万円 |
| その他(ホームページ制作・スタッフ採用・備品購入など) | 100万~700万円 |
上記の表からもわかるように、内装工事にかかる費用と設備の導入費用が初期費用の大半を占めます。
これは耳鼻咽喉科には、防音室の設置やCT検査装置の導入が必要なためです。
ただし、導入する医療機器は新品のものではなく、中古品を選んだりリースを活用したりすれば費用を抑えられる可能性も十分にあります。
運営費用
開業後もクリニックの経営を継続していくためには、開業資金として運営費用の準備も必要です。
その具体的な費用の目安は、2,000万円程度です。
運営費用には、人件費や固定費、さらに変動費も含まれます。
これらは、開業後に売上が安定しない時期にも支払う必要があるため、それぞれおよそ6か月分は準備しておきたいところです。
なお、一般的には売上の半分以上が運営費用に充てられるので、経営を安定させるには人件費や固定費のバランスが重要となります。
耳鼻咽喉科の開業医の平均年収

厚生労働省が令和5年に実施した「第24回医療経済実態調査」によると、耳鼻咽喉科の開業医の平均年収は、2022年時点で約2,626万円でした。
ただしこの金額は、クリニックの収益から賃料や給与、また医薬品などの経費を差し引いたものです。
開業医個人の手取り収入は、ここからさらに所得税や住民税などが引かれた金額となるため、お伝えした年収額は目安として押さえておくとよいでしょう。
耳鼻咽喉科は、幅広い年代の患者さんを診るため安定した需要があり、花粉症やインフルエンザのシーズンには来院患者数が大きく増える傾向にあります。
スムーズな診療を行えるよう体制を整えたり、早朝や夕方の診療を増やしたりと、繁忙期のニーズに対応することでさらなる年収アップが期待できます。
参照元:厚生労働省「第24回医療経済実態調査p302、p495」
耳鼻咽喉科の現況

繰り返しになりますが、耳鼻咽喉科は幅広い年代の患者さんに需要がある診療科のため、地域医療におけるニーズは依然として高い状況です。
厚生労働省の「医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、2023年時点で耳鼻咽喉科を標榜するクリニックは5,681施設、施設の総数に対する割合は5.4%です。
施設数がもっとも多い内科は64,747施設、総数に対する割合が61.7%という結果から、競合が少なく専門性を発揮しやすい状況にあると考えられます。
しかし、人口減少の影響で全国的に耳鼻咽喉科医の数はそれほど増えておらず、地域によっては医師が不足しているのが現状です。
また、診療報酬の改定や高額な医療機器の導入によるコスト面の負担にくわえ、医療スタッフの確保が難しいといった課題も存在します。
耳鼻咽喉科は安定した需要によって開業の余地があり、そして集患が見込める立地の選定や競合と差別化を図るための経営戦略が、開業成功の鍵となるでしょう。
参照元:厚生労働省「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況p5」
参照元:一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「耳鼻咽喉科医師数に関する全国調査」
耳鼻咽喉科開業のメリット

耳鼻咽喉科を開業するメリットとして、個人の裁量で自由に診療できる点が挙げられます。
耳鼻咽喉科は幅広い年代の患者さんに需要があるだけでなく、花粉症や中耳炎などの慢性的な疾患にも対応しているため、安定した集患が見込めます。
さらに開業医の場合は、クリニックの運営方針や診療時間を自分で決められるので、自由度の高い働き方が叶うでしょう。
また、ほかの診療科よりも全国的に施設数が少ないため、立地によってはより深く地域医療に関わることができます。
特に耳鼻咽喉科医が不足している地域では、遠方の患者さんが来院することも少なくありません。
近隣はもちろん、幅広い地域の患者さんにも足を運んでもらえれば、経営の安定性も高まります。
開業医のメリットについてもっと詳しく知りたい方はこちら
関連記事:開業医とは?やりがいやメリット・デメリットを詳しく解説!
耳鼻咽喉科開業のデメリット
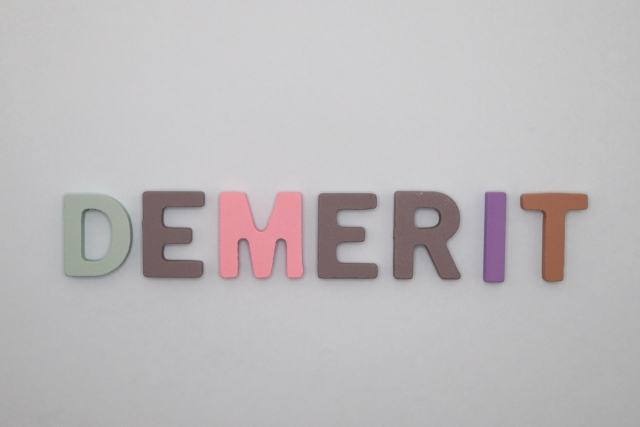
一方、耳鼻咽喉科の開業には防音室の設置や高額な医療機器の導入など、多額の初期費用が必要になります。
競合するクリニックと差別化を図るためにも設備投資は必須となり、集患が安定するまでは投資額と売り上げのバランスが取れずに、厳しい経営状況が続く可能性もあります。
さらに、耳鼻咽喉科はほかの診療科と比較して診療単価が低い傾向にあり、より多くの患者さんを診なければ理想の収入を実現するのが難しい点も、デメリットの一つです。
医師として患者さんから信頼を得るのはもちろん、経営者として運営費の管理やスタッフの採用など、診療以外にも多くの責任を負わなければなりません。 クリニック開業をご検討の医師の方へ マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。 また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
しかしその分、診療内容や運営方針を自分の裁量で決められる自由があり、勤務医とは違ったやりがいを感じられるはずです。
まずは、サービス概要と案件情報をご覧ください。
耳鼻咽喉科の開業を成功させるポイント
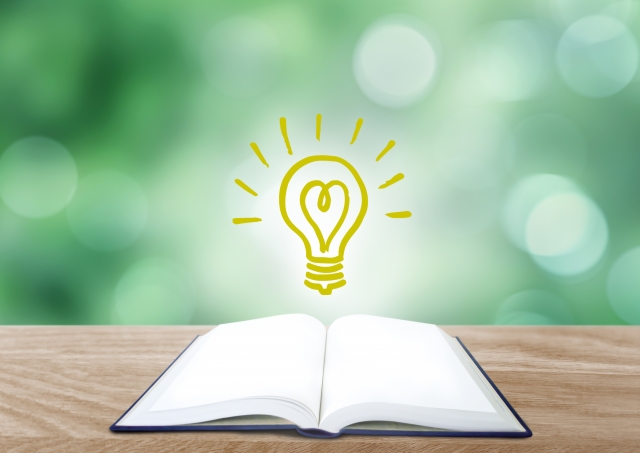
耳鼻咽喉科の開業を成功させるためには、地域のニーズに合わせた戦略が重要です。
主なポイントを、以下の8つに分けて紹介します。
耳鼻咽喉科の開業を成功させるポイント
- ポイント①適切な立地を選ぶ
- ポイント②患者さんのニーズに合わせた内装を心がける
- ポイント③集患対策を徹底する
- ポイント④診療の効率化を検討する
- ポイント⑤専門性の高い治療を取り入れる
- ポイント⑥感染症対策を徹底する
- ポイント⑦往診に対応する
- ポイント⑧ほかの診療科と連携する
ポイント①適切な立地を選ぶ
耳鼻咽喉科の開業を成功させるには、集患が見込める立地を選ぶことが大切です。
耳鼻咽喉科では、風邪や花粉症、まためまいなど身近な症状にも対応するため、アクセスの良さは集患数に直結します。
また、ターゲットとなる患者さんを意識した開業エリアの選定も重要です。
小児耳鼻咽喉科であれば、子どもが集まる保育園や小学校の近くに開業することで、より多くの患者さんの来院が見込めます。
一方、オフィスワーカーをターゲットとする場合は、都市部のビジネス街を開業場所に選ぶと集患しやすくなります。
ただし、耳鼻咽喉科は内科や小児科と競合するケースもあるので、周辺の診療科ごとの施設数や患者さんの流入数を調べておきましょう。
競合となるクリニックが少ない地域を選ぶことで、開業が成功する可能性が高まります。
ポイント②患者さんのニーズに合わせた内装を心がける
耳鼻咽喉科には幅広い年代の患者さんが来院するため、内装にも配慮が求められます。
子どもが多い地域では、待合室にキッズスペースを設けることで、お子さま連れの患者さんでも安心して来院できます。
また、高齢の患者さんが多い地域の場合には、身体の負担を減らすために段差をなくしたバリアフリー設計を取り入れるのも有効です。
さらに、診察までの待ち時間を患者さんが快適に過ごせるよう、座席の十分な確保や空気清浄機の設置も欠かせません。
このように、患者さんの満足度を高める内装設計は、再来患者さんの獲得や口コミの拡大につながります。
ポイント③集患対策を徹底する
開業後の安定した経営には、地域の患者さんに継続的に来院してもらう仕組みづくりも不可欠です。
Web予約システムや整理券システムを導入して利便性を向上させるほか、ホームページやSNSで診療内容を発信すると、クリニックの認知度を高められます。
さらに、花粉症やインフルエンザなどの季節ごとの症状に対応した診療体制を整えていることをアピールするのも効果的です。
Webを活用した集患対策にくわえ、看板やチラシも使用することで、幅広い世代へのアプローチが可能になります。
地域の専門医として認知度が向上すれば、安定した集患が期待できます。
また内覧会を実施することで集患対策にもなります。内覧会に関して詳しくはこちらで紹介しています。
関連記事:クリニック開業時の内覧会とは?流れやメリットを解説
ポイント④診療の効率化を検討する
多くの患者さんを診られるように診療を効率化することも、売上の向上につながります。
耳鼻咽喉科は、ほかの診療科と比べて診療単価が低いので、診療効率を高めて1日の診療件数を増やす必要があります。
診療をスムーズに進めるためには、時間ごとの患者さんの人数を調整するほか、スタッフの移動や診察の準備にかかる時間の削減が不可欠です。
また、Web予約システムや整理券システムを導入すれば、スタッフの受付業務や電話対応の負担を軽減できるだけでなく、患者さんの待ち時間も減らせます。
スタッフの動線を考慮したうえで、診察室や検査室などのレイアウトを設計することも、診療の効率化に役立ちます。
1日に多くの患者さんを診ることができれば、収益の安定にくわえ、患者さんの満足度も向上するはずです。
ポイント⑤専門性の高い治療を取り入れる
一般的な外来診療とあわせて、専門性の高い治療を取り入れることも、競合のクリニックと差別化するために重要なポイントです。
たとえば、副鼻腔炎に対する日帰り手術、またアレルギー性鼻炎やいびきに対するレーザー治療などは、患者さんにとって通院の負担が少ないため需要が高まっています。
また、花粉症の注射治療や難聴の遺伝子検査などは自費診療として扱うケースもあるので、積極的に取り入れたいところです。
こうした先進的な治療の導入は、地域での存在感を高めるとともに、自費診療を増やして収益の安定にもつながります。
ポイント⑥感染症対策を徹底する
耳鼻咽喉科は、ほかの診療科と比べて院内感染のリスクが高いので、万全な感染症対策も欠かせません。
鼻や喉に症状を抱える患者さんが多く訪れる耳鼻咽喉科では、くしゃみやせきによる飛沫が発生しやすく、院内感染のリスクが高まります。
待合室には空気清浄機や換気設備、また隔離室などを設けて、飛沫を防止することが重要です。
こうした取り組みは感染リスクを抑えるだけでなく、患者さんから“安心して通えるクリニック”として選ばれる要因となります。
ポイント⑦往診に対応する
往診の対応は集患効果を高め、結果として開業の成功につながるでしょう。
近年、少子高齢化の影響により、耳鼻咽喉科にも往診のニーズが拡大しています。
厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」では、認知症の危険因子として難聴が挙げられ、発症の予防が推進されています。
これにより、認知症の予防には耳鼻咽喉科医による聴覚管理が役立つとされ、多くのクリニックで訪問診療の整備が進められている状況です。
また、通院が難しい高齢者や寝たきりの患者さんは、自宅でえん下障害を引き起こす可能性が高い傾向にあります。
えん下障害は重症化すると生命に関わる危険性もあるので、耳鼻咽喉科医による自宅での適切なケアが求められるわけです。
このような背景から、通院が困難な患者さんへの往診対応は、地域医療における役割を果たすだけでなく、社会的ニーズに応えることにもつながるといえます。
さらに、在宅医療は診療報酬の加算も期待できるため、経営面でもプラスにはたらきます。
参照元:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)p11」
ポイント⑧ほかの診療科と連携する
耳鼻咽喉科は単独でも需要がありますが、ほかの診療科と連携することでさらに集患効果を高められます。
特にクリニックモールでは、内科や小児科、また眼科などのさまざまな診療科が集まっており、患者さんを紹介し合える体制が整っています。
このような場所で開業すれば、耳鼻咽喉科では対応できない症状のある患者さんが来院された場合も安心です。
たとえば、耳鼻咽喉科にめまいや頭痛の症状がある患者さんが来院したものの、神経の障害や脳の病気が疑われ、内科を紹介するケースです。
反対に、内科を受診した患者さんに副鼻腔炎や中耳炎の症状があり、耳鼻咽喉科を紹介されるケースもあるでしょう。
クリニックモール内での連携は、医師やスタッフ同士の情報共有が可能となり、経営面でも効率的な運営を実現できます。
また、同じ場所で複数の診療科を受診できるため患者さんにとっても利便性が高く、再来院につながりやすいのも利点です。
耳鼻咽喉科の開業を成功させるには、地域のニーズに合わせた戦略が重要

耳鼻咽喉科はさまざまな年代の患者さんに需要がある診療科のため、開業の余地は十分にあります。
しかし、ほかの診療科に比べて診療単価は低い傾向にあるので、診療の効率化や往診の対応を検討し、1日の診療件数を増やすことが重要です。
また、先進医療の提供や近隣のクリニックとの連携も、再来患者さんの獲得につながります。
地域の特性や患者さんのニーズに合わせて綿密な戦略を立てることが、開業成功の鍵となるでしょう。
「クリニック経営に不安がある……」という方は、マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートをご利用ください。
医師の開業を成功に導くため、スタートアップからフォローアップまで包括的にサポートいたします。














