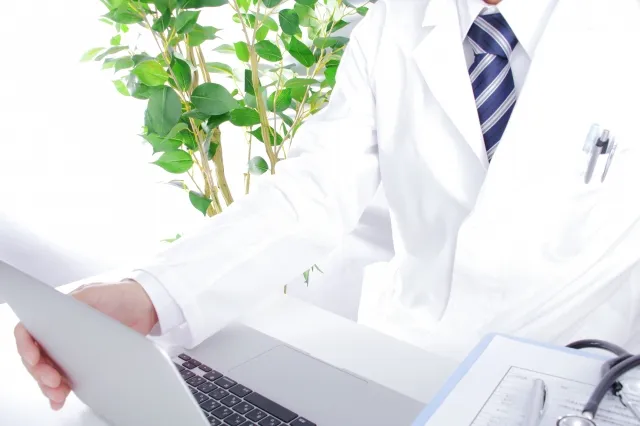患者さんに来院してもらえない場合、経営が立ち行かなくなる可能性があるため、集患および増患対策は特に力を入れたいところです。
そこで本記事では、開業したクリニックに患者さんが来ない理由と、その対策方法を詳しく解説します。
クリニックの経営を安定させたい方や、将来的に開業をお考えの方はぜひご一読ください。
関連記事:開業医とは?やりがいやメリット・デメリットを詳しく解説!
クリニック開業をご検討の医師の方へ
マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。
また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
まずは、サービス概要と案件情報をご覧ください。
目次 閉じる
開業医のクリニックに患者さんが来ない理由

クリニックの来院数が伸び悩んでいる場合、以下のような理由が考えられます。
インターネット戦略の不足
広報活動でインターネットを活用しきれていない場合、クリニックの存在が認知されない可能性があるため、集患数を増やすのは困難でしょう。
来院する患者さんの多くは、診察時間や設備といったクリニックの基本的な情報をインターネット上で確認します。
つまりホームページを開設していない場合、患者さんからクリニックの存在を認知されないおそれがあるわけです。
またホームページを開設しても、記載する情報が不足していると、どのようなクリニックなのかを判断できず、結果として来院につながりにくくなります。
近年は、診察を受けるクリニックを、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで調べた情報をもとに決める方もいます。
効果的に集患するには、ホームページの開設にくわえて、SNSの活用といった施策も必要です。
立地が悪い
クリニックの立地が悪い場合、集患数・増患数の向上が見込めないおそれがあります。
駅からクリニックまで、徒歩で15分以上かかる場合や順路が複雑な場合、患者さんに通いにくい印象を与えるうえに、駅周辺の競合のクリニックに流れるリスクが生じます。
また、クリニックに訪れる患者さんは体調が万全ではないため、訪問しやすい立地を選ぶに越したことはないのです。
経営を安定させるには、離れた地域からの来院にも配慮しておきたいところです。
クリニック開業する際に役立つ立地の選び方について詳しくはこちら
関連記事:クリニックを開業する際の立地はどのように選べばよい?
患者さんとのコミュニケーション不足
患者さんとのコミュニケーションが不足していると、再診率が上がらず、増患数が伸び悩む可能性があります。
たとえ優れた医療を提供しているクリニックでも、治療や処方する薬に関する説明が不足している場合、患者さんとの信頼関係を築くことは困難です。
大型の病院と比べて小規模なクリニックは、周辺に住む患者さんの心のよりどころにもなるため、円滑なコミュニケーションも必要とされるのです。
患者さんの症状や境遇、心情に寄りそい、適正な医療の提供はもちろん医療サービスの充実を図ることで、集患、増患を目指していきましょう。
待ち時間が長い
待ち時間が長くなると、クリニックを訪れた患者さんは不満を募らせるため、以降の受診につながらなくなるおそれがあります。
再診患者さんに「待ち時間がいつも長いな……」と思われれば、競合のクリニックに流れてしまうかもしれません。
さらに、インターネット上に待ち時間の長さを指摘した口コミが投稿されれば、初診を検討している方にも来院を避けられる可能性があります。
患者さんの満足度を上げ、来院を促すには、前述したコミュニケーションにくわえてスムーズな案内を可能にするクリニックの体制づくりも必要です。
強みを押し出せていない
開業したクリニックの周辺に、すでに競合のクリニックが存在する場合、異なる強みや差別化できる要素がなければ、患者さんを取り込むのは難しいでしょう。
駅前や主要道路の近辺をはじめとする通院しやすい立地には、競合のクリニックが多い傾向があります。
このような立地でクリニックを経営する際は、競合ではなく自院を選ぶ理由を、患者さんに見いだしてもらう必要があるのです。
そのため、周辺に既存のクリニックがある場合は、ご自身のクリニックが持つ強みを患者さんに提示することが、来院数を増やすポイントとなります。
医師のスキル・知識の不足
医師のスキルや知識が不足している場合、来院数が伸びない可能性があります。
患者さんに病気や治療の詳細をわかりやすく伝えることは、医師の重要な仕事の一つです。
患者さんを納得させる説明ができない場合、不信感を与えてしまい、結果的に再診を避けられる要因になります。
また近年は、広報の一環として、病気の症状や治療方法をSNSやホームページのコラムで解説するクリニックもあり、患者さん自身が事前に情報を集める機会が増加しています。
なかには、調べた情報と異なる点を見つけ、「嘘を言われているのではないか……」と疑うケースも少なくありません。
このような事態を避けるには、クリニックの開業後も研さんを積み、患者さんに納得してもらえる説明をできるように備えておくことが重要です。
スタッフの教育不足
医師のスキルが十分でも、受付や看護師といったほかのスタッフへの教育や指導が行き届いていない場合、クリニックの評判が下がり、来院数が減少するおそれがあります。
特に受付の対応は、多くの口コミで指摘される要素の一つです。
冷たいあいさつや不親切な対応をされた患者さんは、スタッフだけではなく、クリニックに対しても不満を抱くため、ほかのクリニックに流れてしまう可能性があります。
クリニックは患者さんの心のよりどころともなるので、居心地の良い環境づくりに向けて、スタッフの勤務態度や業務の教育を徹底することが必要となります。
クリニックに患者さんが来ない場合の対策

クリニックの患者さんを増やすためには、認知度と医療の質の両面で向上を図り、口コミなどからの初診率と再診率を高めることが必要です。
ここからは、来院数を増やす効果的な8つの対策方法をお伝えします。
対策①看板を設置する
看板の設置は、認知度向上を速やかに図れる対策の一つです。
来院数を増やすにあたり、まずはクリニックの存在を知ってもらわなければなりません。
クリニックの最寄り駅や、主要道路に看板を設置すれば、周辺の患者さんを取り込みやすくなるでしょう。
設置する看板には、クリニックの名称や電話番号にくわえて、診療科名や提供する医療、簡単なアクセス方法などの情報を記載することで、より効果的に来院を促せます。
対策②SNSを活用する
周辺地域にくわえて、ほかの地域の患者さんを取り込むには、SNSでの情報発信が有効です。
インターネットの普及に伴い、クリニックを選ぶ際の情報収集でSNSを活用する方が多くなっています。
来院を促したい患者さんに向けて病気や治療に関連する情報を発信し、クリニックの存在を知ってもらうことで来院に期待できます。
また、患者さんが来院をイメージしやすくするために、施設内やスタッフなどを撮影し、クリニックの雰囲気がわかる情報を発信するのも効果的です。
実際に情報を発信する際は、活用する各SNSの特徴を理解したうえで投稿内容を考えましょう。
X(旧Twitter)では病気や治療法に関する説明を、画像がメインとなるInstagramではクリニックの外観や待合室の写真といったかたちで、投稿内容を分けるのがおすすめです。
なお、SNSで病気や治療法などの情報を発信する際は、誇大広告にならない範囲での説明に終始し、医療広告ガイドラインに抵触しないように注意してください。
対策③患者さんへの接し方を改善する
患者さんとの適切なコミュニケーションによって信頼関係を構築できれば、クリニックの増患につながります。
医師やスタッフへの印象はクリニック全体の評価に直結するため、医療の提供だけではなく、患者さんの心情に寄り添うことも必要です。
たとえば、明るいあいさつや積極的に話を伺う姿勢は、患者さんに安心感を与えます。
こうした一つひとつの心がけを徹底し、クリニック全体で居心地の良い雰囲気をつくることが患者さんの満足度を向上させ、定期的な来院につながるのです。
もしも、医師やスタッフのコミュニケーションに改善の余地がある場合は、指導・教育を徹底しましょう。
対策④再診予約を促す
患者さんの来院時に、次回の来院予約を取ってもらうことで、再診率を高められます。
来院時に次回の予約が取れていない場合、再度来院してもらえる可能性は低くなります。
そのため、患者さん側からの予約を待つだけではなく、クリニック側が積極的に予約を促す姿勢も必要になるのです。
治療後の経過観察が必要な患者さんであれば、定期健診といったかたちで再来院を促せるうえに、信頼関係の構築にもつなげられます。
対策⑤院内環境を改善する
待合室をはじめとする院内環境の整備も、集患率を高めるうえで重要な対策です。
来院した患者さんは多くの時間を待合室で過ごすため、居心地の良い空間を用意することで、好印象を与えられます。
待合室のほか、お手洗いも多くの患者さんが利用するので、これらのスペースを清潔に保つように心がけてください。
また、ウォーターサーバーやWi-Fiを設置すれば、万が一待ち時間が長くなる場合でも、より快適に過ごせるようになるはずです。
これにくわえて、お子さま連れの患者さん向けに、絵本を用意しておくのもよいでしょう。
対策⑥近隣の競合施設との差別化を図る
周辺に競合のクリニックがある場合、独自のメリットを提示して差別化を図るのも有効な対策です。
たとえば、自院と競合のクリニックの診察時間が重なる場合、診察時間を伸ばしたり、あえてずらしたりすることで来院数の増加に期待できます。
また、予約システムにより診察までの流れをスムーズにすれば、忙しい患者さんにとってのメリットとなるでしょう。
なお、クリニックの体制を改める際は、既存の患者さんを混乱させないためにも慎重な判断が必要です。
対策⑦SEO・MEO対策をする
インターネットを通じた広報活動が重視される現代において、“SEO対策”や“MEO対策”は、認知度を上げる有効な施策の一つです。
SEO対策とは、googleをはじめとする検索エンジンで、自社のホームページを上位に表示させてアクセス数を増やし、顧客の獲得を目指す施策のことです。
ホームページ上に、ブログやコラムといったかたちでユーザーにとって有用な情報を提示できれば、上位に表示されやすくなります。
一方MEO対策は、地図検索での上位表示により顧客の獲得を図る施策です。
たとえば、「千代田区 内科」といったキーワードで検索した際、自院が上位に表示されれば、千代田区で内科クリニックを探す患者さんからの認知度を高められます。
地図検索の上位に表示される基準は、口コミの数および高評価の数といわれています。
これらの施策を実行し、患者さんがインターネット上で自院の情報を目にする機会が増えれば、おのずと来院数の増加につながるというわけです。
いずれの施策も、ご自身で行う場合はコストがかかりません。
しかし、多くの手間がかかるうえに、コア業務に支障をきたすおそれもあるので、専門業者への委託を検討するのも一つの手です。
対策⑧口コミに対応する
インターネット上の口コミを参考にすることで、集患および増患に役立てられます。
口コミには、来院した患者さんのリアルな意見が反映されるため、これらを参考に改善策を講じれば、クリニックの満足度が向上し、集患・増患につながるというわけです。
また、厳しい意見が寄せられた際は、事実確認を行ったうえで真摯に向き合うことで、患者さんからの信頼を取り戻せる場合もあります。
開業前に押さえておきたいポイント

クリニックの安定した経営を実現するには、開業後の施策だけではなく、開業前の準備も重要です。
将来的に開業をお考えの方は、運営が立ち行かなくなる事態を避けるために、以下で紹介するポイントを押さえておきましょう。
ポイント①立地の選定
クリニックの安定した経営には、適切な立地選びが不可欠です。
立地は開業後の来院数に影響するため、利便性や周辺施設の利用者数など、さまざまな要素を分析したうえで決定します。
このとき、必要となる資金を抑えられるからといって立地を安易に決めてしまうと、来院数が伸びず経営が困難となるおそれがあります。
一度開業すると、ほかの場所へ移るには多大なコストがかかるので、クリニックの立地は慎重に判断しなければなりません。
資金に関して気になる方は以下の記事も合わせてご覧ください。
関連記事:クリニックの開業に必要な資金はいくら?診療科目ごとに解説
ポイント②マーケティング戦略
マーケティング戦略の策定は、クリニックを開業するうえでも重要なポイントです。
クリニックには高品質な医療の提供も必要ですが、来院数が不足してしまうと経営は困難となります。
そのため、経営者として「どのように認知度を高めるか」「どのように来院を促すか」といった戦略的な視点も必要になるのです。
開業後に対策を講じることも有効ですが、計画や目標をあらかじめ明確化しておけば、より適切な施策の実行を可能にし、患者さんの来院につなげやすくなります。
ポイント③院内環境および運営体制の整備
来院した患者さんが快適に過ごせる院内環境や、スムーズな案内を可能にする運営体制も、開業前にきちんと準備しておきたいポイントの一つです。
クリニックに来院する患者さんは、再診である場合が多いといわれています。
そのため、経営を安定化させるには、患者さんの満足度を上げ、2回目以降の来院を検討してもらうことが重要となるのです。
たとえば、待合室を清潔に保ちつづければ、来院した患者さんに安心感を与えられます。
また、予約システムの導入や、医師やスタッフの効率的なオペレーションを整備することで、短い待ち時間での案内が可能となり、患者さんの満足度の向上につながります。
クリニック開業をご検討の医師の方へ
マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。
また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
まずは、サービス概要と案件情報をご覧ください。
クリニックを開業するのが不安な場合

クリニックの開業に不安を感じる方は、開業コンサルタントへ相談することで専門的な知識と経験をもとに、実践的なアドバイスを受けられます。
安定した経営を実現するには、開業前の準備や、開業後の施策といったさまざまな準備が必要です。
しかし、効果的な計画・施策となるかどうかはクリニックによって異なるので、実行する際は慎重に判断しなければなりません。
その点、開業コンサルタントを利用すれば、事業計画書の策定や立地の選定、集患を促す施策の提案など、クリニックの安定的な経営に役立つさまざまな支援を受けられます。
ご自身の負担を減らしつつ、効率的に開業を進めたい方におすすめです。
開業医になっても患者さんが来ない理由は集患対策が不十分なため

今回は、開業したクリニックに患者さんが来ない理由を、対策方法とともに解説しました。
クリニックの経営を安定化させるためには、高品質な医療の提供にくわえて、集患および増患の対策も重要です。
具体的には、看板の設置やSNSでの情報発信、院内環境の整備などが挙げられます。
クリニックを開業する際は、これらの施策を綿密に計画しておけば、安定した経営につなげやすくなるでしょう。
開業医になることをお考えの方は、医療を専門とする開業コンサルタントに相談するのがおすすめです。
マツキヨココカラのクリニック開業サポートは、立地の選定や事業計画の策定、広報活動といったさまざまな支援を実施し、開業を後押しします。
クリニック開業支援ならマツキヨココカラクリニック開業サポート